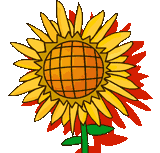|
このページは 2008年 01月 06日 12時08分55秒に更新されました。 |
電車や電気機関車は、自車にエネルギー源を積載せずに外部から送電線を通して電気の供給を受けながら、走行しています。これは他の乗り物にはない特徴で、その電気を採り入れる装置を「集電装置」(current collectr)と呼びます。 今まで使われて来た鉄道の集電装置には、以下のような種類があります。●架空電車線(架線)とパンタグラフ●架空電車線(架線)とビューゲル●架空電車線(架線)とポール●第三軌条と集電子(集電靴) これらの方式には、それぞれ長所や短所があり、技術的な進歩や使用する鉄道の状況、種類によって取捨選択されています。 パンタグラフ(pantograph)は、現在の鉄道(在来線や新幹線など)で最も広く使われている集電装置です。電車や電気機関車などの屋根上に取り付けられた、ひし形の装置がパンタグラフです。写真は、1950年代の国鉄や私鉄電車に広く使われていたPS13形パンタグラフです。近年では1本のアームで「く」字形になったひし形ではないパンタグラフも登場しています。いずれも絶縁碍子を間に挟んで屋根上に取り付けられ、車体とは電気的に絶縁されています。 従来からのパンタグラフは、折りたたみのできるひし形の枠組があります。ひし形になっているのは、車両が前後どちらの方向に進んでも、同じ作用をさせるためです。その上に弓の形をした集電舟と呼ばれる部品が取り付けられています。この枠は、架空電車線(架線)の高さの変化に追随して、集電舟がスムーズに上下動するようにリンク機構が組み込まれています。また、集電舟の端が湾曲しているのは、分岐などで架線の位置が左右に離脱したとき、枝分かれした線に引っかからないようにするためです。
集電舟の中央部には、架線に接触する集電子となるすり板がついています。すり板は、電気的な接触抵抗が小さく、集電容量の大きい磨耗の少ない材料が選ばれています。初期の頃は銅すり板や炭素すり板が使われていました。しかし、銅すり板は磨耗の大きな点が問題でした。また、炭素すり板は架線との接触抵抗が大きく、過大電流が流れたとき、架線を溶断させる恐れもありました。そのため、戦後になって銅粉末やグラファイトなどの粒子を焼き固めた「焼結合金すり板」など集電特性のよいものが開発され、広く使われるようになりました。この場合でもすり板は、約2万km走行ごとに交換されています。さらに、最近では架線との離線が少ない性能の良いパンタグラフが開発されたことからスパーク事故が防げ、架線側の磨耗を少なくできる炭素系のすり板が登場しています。 パンタグラフの集電舟は、走行中も架線に安定して接するように、一定の圧力で押し上げられています。押し上げる力は、バネが使われています。 電車用のパンタグラフは、電気機関車よりも集電容量が小さいため、小型に設計できます。そのため、軽量で構造も簡便なバネ上昇式を使っています。写真のPS13形パンタグラフは、簡易設計をしたバネ上昇式です。 一方、電気機関車、特に旧型の直流電気機関車では、大容量の集電装置が必要でした。そのため、パンタグラフは大型のものを2基備え、下げ操作を重力で行う空気上昇式が一般的でした。ただし、交流電気機関車では、架線電圧が高いため採り入れる電流は小さくて済み、パンタグラフも小型になりました。また、高速列車用のパンタグラフは、架線の速い動きや振動にも鋭敏に追随できる性能が求められるため、集電舟などの支えに小さなバネを組み込み、可動部分の重さ(等価質量)を小さく設計しています。※ビューゲル、ポールについては改めてご紹介いたします。
[ 35] 鉄道博物館 展示資料紹介 [PS13形パンタグラフ]
[引用サイト] http://www.railway-museum.jp/exhibition/110.html
|
戻る
一人暮らしの情報満載
一人暮しの情報満載
暮らしと生活、田舎暮し、一人暮し、美容暮し、家計暮し、節約暮し、洗濯暮し、
家計簿暮し、田舎暮らしの物件、住まい生活、暮らしと生活 |
情報の宝船【インフォマガジン】
暮らしと生活に役立つ無料情報が満載です。(いつでも解除できます)
今なら 『簡単すぎる!暮らしと生活をもっともっと幸せにする潜在意識活用法』のレポートをプレゼント!
3秒後に手に入れることができます。
>>詳細はコチラ |
|